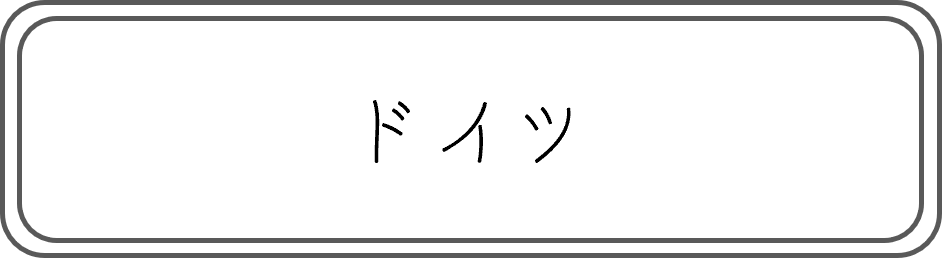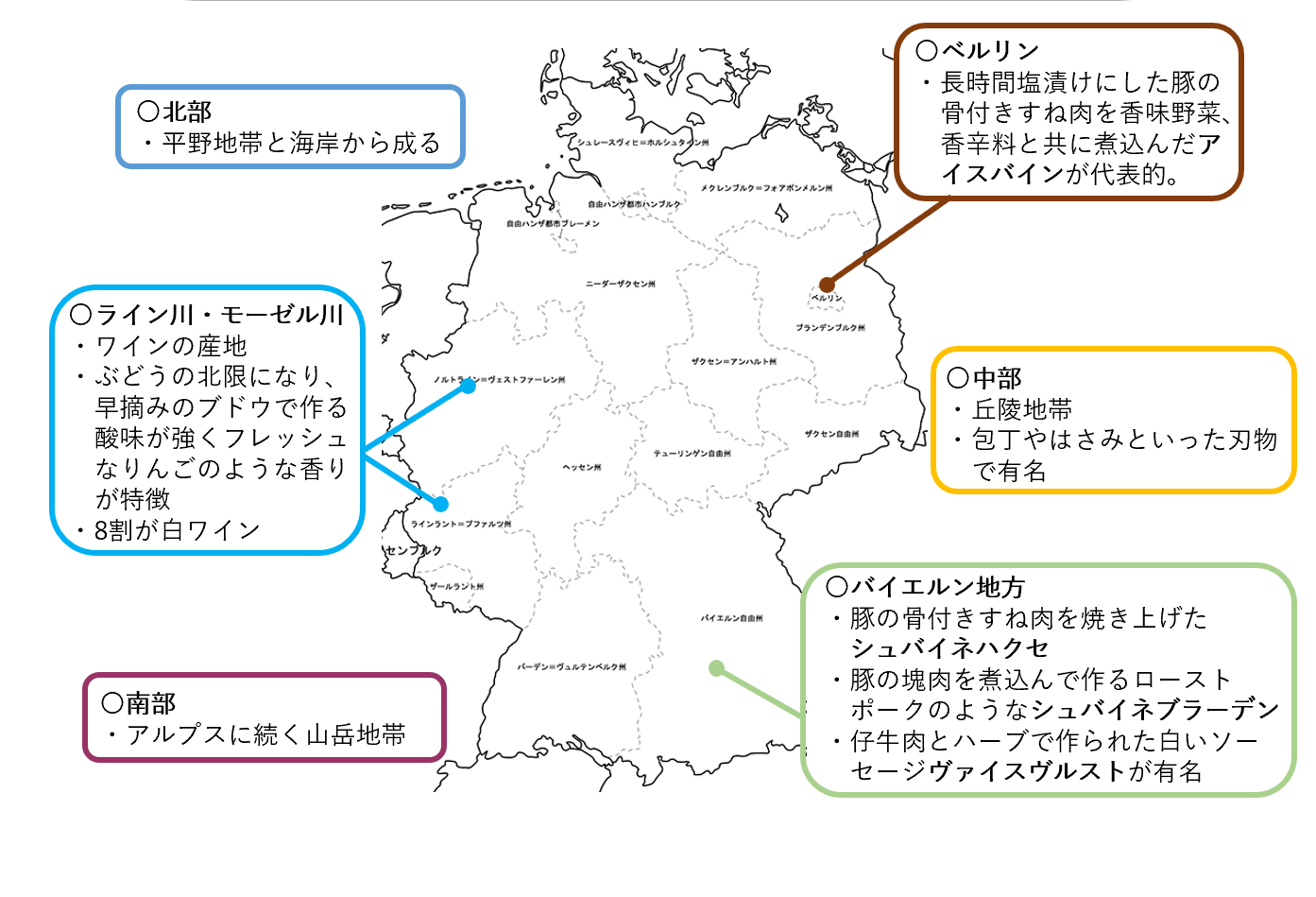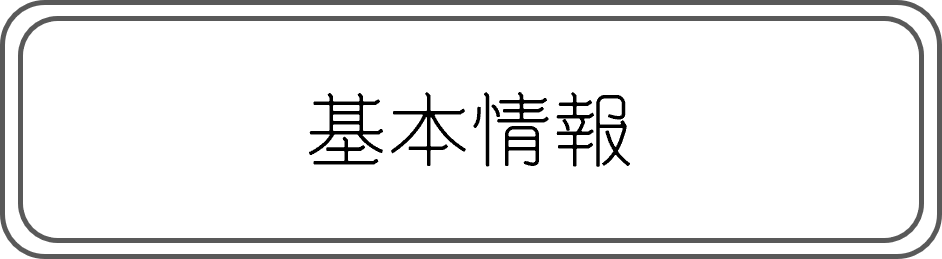食文化
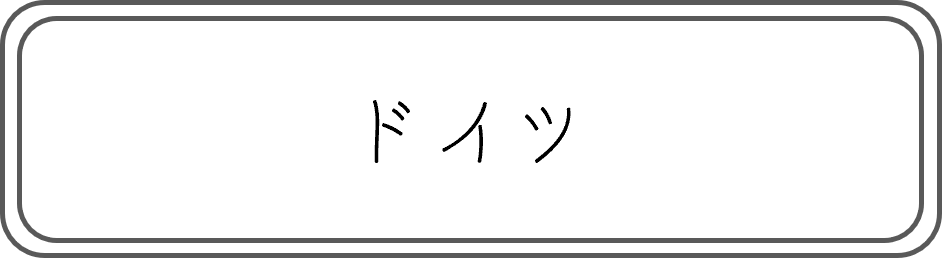
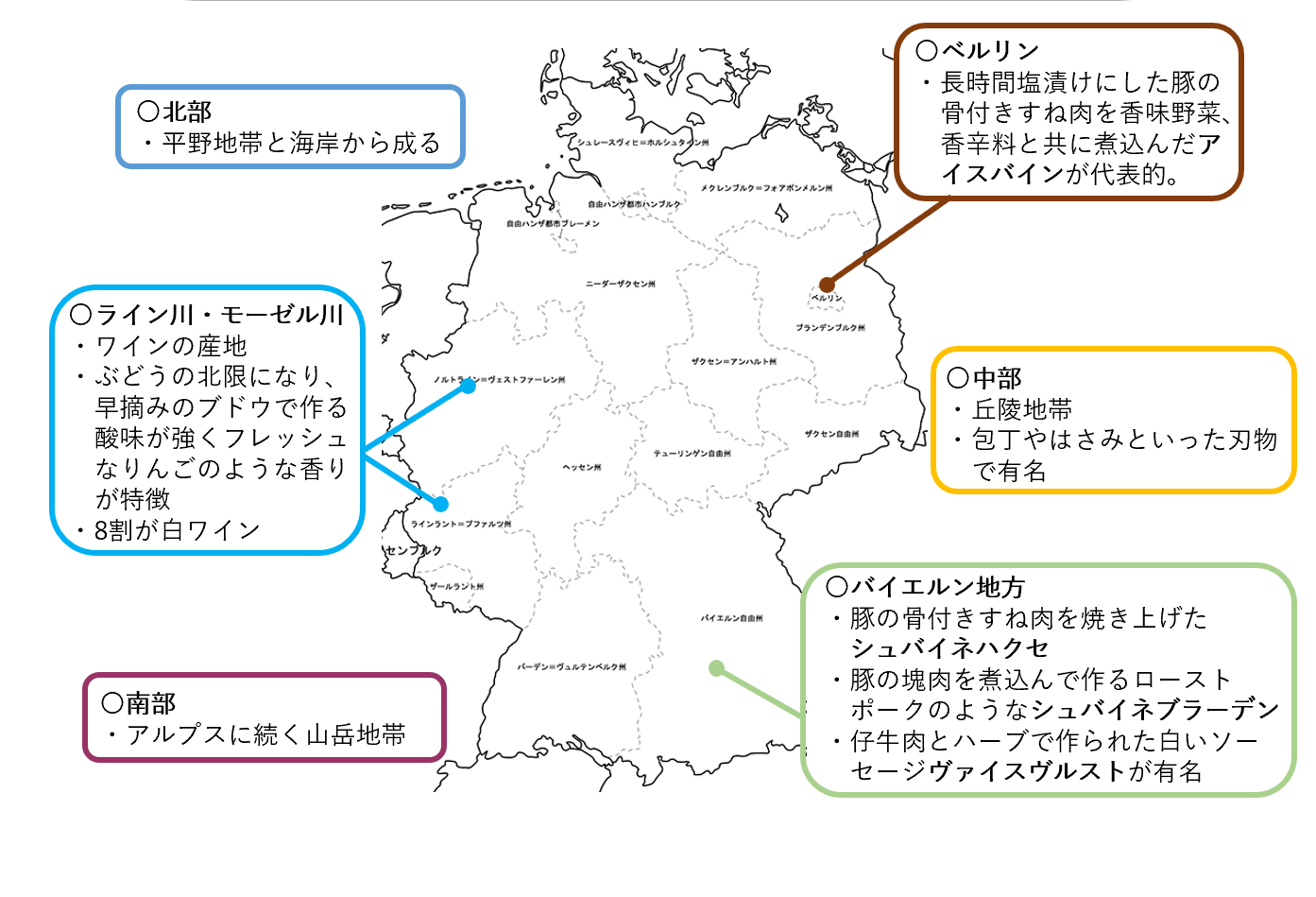
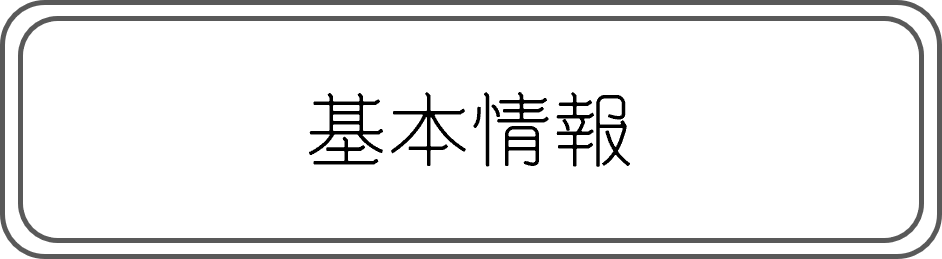
- 堅実で勤勉、合理性を重んじる国民性。
→洗練、美味は後回し
- 一皿で済ませられる経済料理が多い。
- 緯度が高いため寒冷地体が多く、自然の恵みの少ない国。
- 冬が厳しいため脂肪が貴重。
→油は栄養素と考えられていた。また、酢が脂肪の代謝を促進するという説もあり、甘酸っ
ぱく仕上げた料理が多い。
- フルーツを料理に用いることが多い(りんご、洋梨、プラム、あんず、サワーチェリー、木
苺、レイズンなど)。
- 酸味を効かせた料理には、ザワーブラーデン、ザワークラウト、にしんの酢漬け、きゅうりのピクルスなどがある。
- 1744年、フリードリッヒ大王が凶作に困ってじゃがいもを食糧にさせた。
→200種類あるパンよりもじゃがいも料理の方が多い。
- 小麦が育ちにくく、ライ麦・大麦の栽培に適する
→ライ麦パンにはライ麦100%のロッゲンザフトブロート、ライ麦70%のロッゲンミッシュブロート、ライ麦30%のバウェルンブロートがある。
大麦はビールづくりに使用される。
- プレッツェルも有名で、水酸化ナトリウムが溶けたラウゲン液というアルカリ溶液を使用することであの焼き色や風味、食感が生まれる。
- ビールは紀元前にケルト人が現在のバイエルン地方で作っていた記録がある。
- ビールの消費量は世界一で、1500の製造元、5000もの銘柄がある。
→淡い黄金色でホップの利いた爽やかな味わいのピルゼンタイプと、やや濃くアルコール度が高いドルトムントタイプがある。
- ソーセージは種類が多く、牛、豚、仔牛、ブタの肝臓、豚の舌、豚の血液などがある。
- 保存食が特徴的で、ソーセージの他にシュトーレン、ストゥルーデル、カイザーゼンメル、レープクーヘン、バウムクーヘン、キャラウェイ、ポピー、ごま、ねずの実などがある。